電気通信大学60年史
今日編1章 電気通信大学の現状
第7節:厚生補導施設
7-1 学生会館
学生会館、通称"学館"は電通大生の憩いの場である。学館は「学生相互及び学生、教職員の人間関係を密にし、学生の課外活動の発展を助けるとともに厚生福祉を進め、学園生活を豊かにするための中心的施設とする」(電気通信大学学生会規則第一条)という目的があり、この目的のために、学館は、部室、共同談話室、大集会室、音楽室、集会室という構成になっている。また設備としては、印刷、複写、ピアノなどがある。集会室を使用するには許可が必要であるが、他の施設の利用は許可の必要はない。
学館が最もにぎわいをみせる時は昼休みである。共同談話室でダベル者、大集会室で卓球をする者、学館前で昼寝をする者、また、囲碁や将棋をする者など、思い思いに学館を利用している。このために学館には、卓球、野球、囲碁、将棋の道具がそろっており、利用者が多く足りないくらいである。昼休み、この学館の周辺は若者たちの声が絶えない。
7-2 学生寮

学生寮は以前の木造2階建て3棟からなる"調布寮"の老朽化のために、1979年(昭和54年)に現在の鉄筋5階建のモダンな寮に改築された。この改築と同時に、寮の名称も"調布寮"から"五思寮”と改名された。
この五思寮は、入寮定員120名で、全員個室である。この他に設備として、共同で使用する補食室、浴室、洗面、洗濯室と便所が各階に2ケ所ずつ設けられている。また、1・3・5階には談話室が設けられている。食堂はなく、西地区の食堂が寮の食堂の機能をも果たしている。
入寮許可期問は2年以内となっており、これは五思寮の目的として、自宅を離れた新入生が大都会の生活に慣れることができ、1日も早く新しい環境の下で学園生活が送れるようにとの配慮からである。したがって、1・2年次学生を優先して入寮させている。
7-3 学生食堂
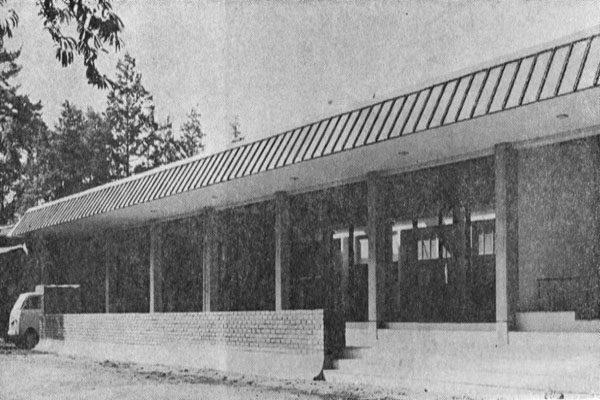
学生食堂は、現在、西地区及び東地区にあり、別々の形態を取りながら運営されて、電通大生の胃袋を満たしている。
西地区は、民間の業者が入り運営されており、寮生の便宜を図るために朝早くから夜遅くまで開いている。東地区の食堂は、生活協同組合(通称生協)がこの経営に当たっている。東地区の食堂は、西地区の食堂に比べ営業時間が多少短くなっている。食堂の形態は、セルフサービスシステムになっている。
東地区の食堂の場合、特に、学館に隣接しているために、食事の場というだけでなく、憩いの場としても、活用されており、食事時をはずれてもかなりの人間がダベリング等に熱中している。したがって、食堂は、電通大の社交場の一つであるといえよう。
7-4 浜見寮
浜見寮は、電通大の学生及び職員のゼミナール、合宿研修、課外活動及びレクリェーション等に使用するための施設として、湘南海岸の一画、鵠沼海岸にある。大きさは、和室8畳4室、7畳半1室、6畳2室である。
浜見寮を使用するには、わずかではあるが使用料金が必要である。また、自炊が出来ないために食堂がある。
浜見寮の使用は、学生の場合、4月、5月、6月に集中しており、各学生の団体が、新入生歓迎を兼ねた合宿として使用されるケースが多くなっている。また、職員の利用は、7月、8月という海水浴シーズンに集中する傾向にある。これは、浜見寮が海岸まで4~5分という海水浴には絶好の場所にある事によるためである。また、毎年夏には、この浜見寮において、ヨットの研修会等も開催されており、かなりの人数の参加者がある。
7-5 保健管理センター
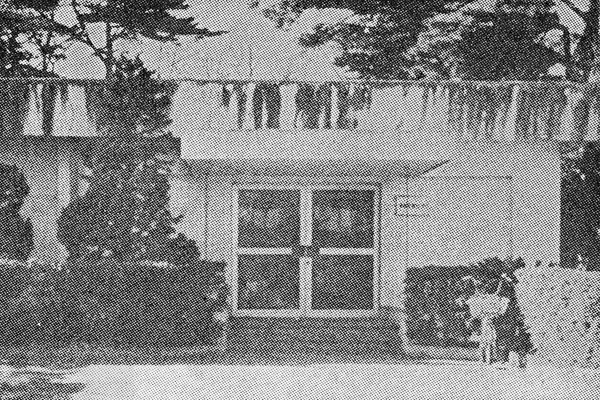
保健管理センターは電通大生の保健管理を完全実施するために設けられている。この目的のために、保健管理センターは主に次のような業務を行っている。「1、保健に関する事項についての指導援助」「2、定期及び臨時の健康診断」「3、健康相談」「4、精神衛生管理」「5、環境衛生と伝染病の予防」の5つの業務である。
このうち、2の定期及び臨時の健康診断であるが、定期診断は毎年全学生を対象に、身長・体重・視力の測定、レントゲン、内科一般を行っている。臨時の健康診断は、定期診断による有疾患者や病気治療後の復学者に対して、適宜行われている。この外にも、週3回の精神面全般の相談を受け、週2回内科一般に対する相談を受け付けている。更に、勉学環境の整備は、教室内の採光、換気等といった細かい点にまで及んでいる。なお、電通大には治療設備がないために、頭痛等の急病や体育実技中等の怪我に対して、救急薬品を備え、常勤の看護婦が治療に当たっている。