電気通信大学60年史
今日編1章 電気通信大学の現状
第4節:短期大学部の現状
4-1 電波通信学科
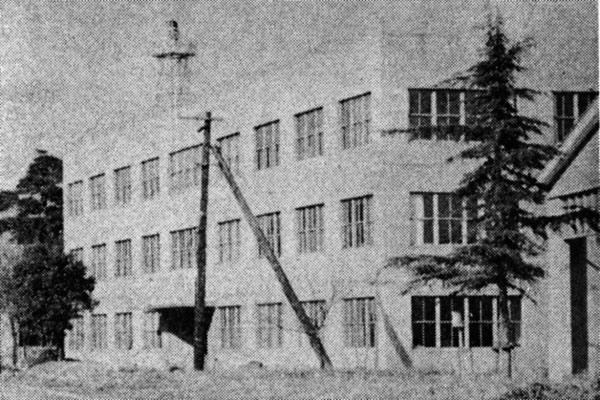
短期大学部電波通信学科は、旧制専門学校制度の廃止と新制大学発足間もないという変革時にあって、従来から本学に伝統的に課せられていた海上、航空及び陸上のあらゆる分野にわたる無線通信その他の通信系の業務に従事する要員の充足などの時代の要請にこたえて、1953年(昭和28年)8月電気通信大学併設短期大学部通信科として本学では最初に設置された3年制の課程の学科である。
発足時の入学生定員は80名で、1953年(昭和28年)9月1日第1回学生として55名が入学、1956年(昭和31年)3月17日第1回卒業式が行われ40名が卒業、このうち38名が船舶、航空、放送、官庁及びその他の通信系に関連のある業務に従事、現在もなお活躍中の者が多い。
1969年(昭和44年)4月、学科の名称を電波通信学科に改称、1978年度(昭和53年度)末までの卒業者及び修了者の総数は1,002名である。
電波通信学科の教授内容は無線通信に関する専門の学芸と技術の教育の他に国際人として活躍できる人材の育成を目指すものとなっており、常に無線通信の運用をつかさどる日本における専門家たるべき意識と、そのために必要な日進月歩の工学系・法律系及びその他を含む広範な分野を現実に含め、また、含めるべく絶えず考慮が払われており、このことは本学の歴史的な教育の一端を担う事実として将来にわたり引き継がれるだろう。
実際には限られた時間のうちで、モールス通信から宇宙通信に関する応用に至るまでの幅広いいろいろな分野を含ませるのはなかなか困難なことではあるが、能率的、かつ、効果的な教育方法とも併せて可能な限り実現のための配慮を行っている。したがって、われわれ教員の研究活動もこれらに関連するものを含めて絶えざる努力が払われている。
現在の研究課題の主たるものとして「モールス通信の人間工学的研究」、「漁業用無線局の設計に関する研究」、「短波ファクシミリに関する研究」、「MLSに関する研究」、「リモートセンシングに関する研究」、「マイクロ波伝送線路に関する研究」、「無線通信に関する諸法令の研究」及び衛星からの情報を直接船舶で利用するための一方式としての「気象衛星情報の船舶への直接導入に関する研究」等が積極的に進められている。
現在までに専任教員として活躍された方々は次のとおりである。
- 教授
- 滝波健吉 市川武夫 酒井敏郎 笹子道雄 伊藤隆之助 清都誠一 吉田春雄
- 助教授
- 朝倉重郎 塩田陽三 根尾泉
- 講師
- 守山喜代松
いずれも無線通信に関する斯界の権威者である。
電波通信学科の現在の専任教員は加藤芳雄教授、宮坂武芳教授、松岡籟之助教授、石島巌助教授及び上芳夫助教授の5名であって、通信運用系及びそれに関連する工学系・法律系などそれぞれの分野における専門家であり、また、教育者である。
また、電波通信学科全般にわたる教育は、学科の専任、その他の関係ある専任教員及び非常勤の教員により行われている。
4-2 通信工学科
- Ⅰ 通信工学コース
-
- 通信工学コースの現状
短期大学部に通信工学科が開設されたのは1958年(昭和33年)4月である。その後、昭和40年代に入りベビーブームの波が全国の大学に押し寄せてきた際、学生定員が増加され、通信工学科(40名)は通信工学科の内容を引き継いだ通信工学コース(40名)と別の内容を持つ通信機械コース(40名)とに分けられ現在に至っている。したがって、通信工学コースの開設以来約20年間にわたり卒業生を世に送り出してきたといってもよいわけで、当初は無線技術者(二級)の養成を目的としていたが、最近では無線技術者として巣立つ学生はほとんどなく、卒業生は広く電子・通信関連の企業で中堅技術者として活躍している。したがって、大学もそのような技術者の養成を主目的としたカリキュラムを用意している。(なお、入学時に定職をもつ勤労学生が多いので、卒業時に就職を希望する者は非常に少ない。)
- 通信工学コースの紹介
通信工学コースの特色は先にも触れたように、本来、無線通信技術者養成にある。しかし、社会の要請にこたえ開講科目は通信工学系のものばかりではなく、電子工学系の科目も用意し、学生の取捨選択の仕方により、通信工学系に重点をおくこともまた電子工学系に重点をおくこともできるようになっている。しかし、本短大は夜間の3年制大学で修業時間が少ないため、広くかつ深く学習するということはなかなか困難で、必然的に基礎的及び概論的科目が多くなっている。すなわち、電磁気学(4単位)、電気回路学(4単位)、電子工学(4単位)及び電子回路学(4単位)を必須専門科目とし、また、人文系(4単位)、社会系(4単位)、自然科学系(19単位)を必須一般教養科目としている。以上のほか、通信系(電気測定学、電子機器学、通信方式、電波伝送学、マイクロ波工学、情報理論等)及び電子系(固体電子工学、物性工学、自動制御、パルス工学、集積回路学、電気機械、ディジタル信号処理等)が開講され、これらの中から16単位以上を履修することになっている。また、通信とコンピュータとの関連性をも教育するため54年度より情報処理概論、計算機演習を開講の予定。学生実験についてその重要性を考慮し、1年半にわたる実験を必須科目(3単位)としているほか、学生が自主的にテーマを設定して実験のできる実験室を開放している。
専任教官は教授1名、助教授2名、助手2名、技官2名で、このほか非常勤講師として電気通信学部の教官及び他の教官の応援を得ている。
- 通信工学コースの将来像
創設以来卒業生(約500名)は通信関連の中堅技術者として大いに活躍しており、本コースが勤労者のための高等教育機関の使命の一端を果たしてきたことは確かである。しかし、昭和50年以降入学者が次第に減少し(入学志願者は定員を超過している)、この原因として社会情勢の変化、夜間教育という勉学上の悪条件、短期大学の社会的位置付けその他いろいろ考えられている。数年来『国立夜間短期大学をいかにすべきか』の問題が文部省をはじめ、各国立短大で真剣に検討され、一部改革が実施されたが、真に『勤労者のための高等教育機関』としての改革はなかなか困難なようで、本短大においても将来計画委員会を設け鋭意検討を重ねている現状である。
- 通信工学コースの現状
- Ⅱ 通信機械コース
-
- 学科紹介
本通信機械コースは、1966年(昭和41年)"通信及び電子工学の基礎を習得し、かつ機械工学の専門知識をも併せもつ中堅技術者の養成"という近代工業にマッチした理想を掲げて、通信工学科の中の一コースとして設立された。
爾来十余年、エレクトロニクスの発展は目覚ましく、特にマイクロコンピュータに代表される情報関連技術の最近の著しい進歩は、生産技術の中心をなす機械工業にも大きな変化をもたらした。すなわち、いまやエレクトロニクス、コンピュータは機械要素の一部と見なされる時代になったといえよう。
このような新時代の要請にこたえ、本コースは、広い視野をもって工業界に貢献できる機械技術者の養成を目的として、教育を行っている。
- カリキュラム
授業内容としては、機械工業に関する基礎専門科目を軸に、エレクトロニクス、コンピュータの基礎科目も開講している。そして、急速な科学技術の進歩に遅れないようなカリキュラムを編成して、いかにして教育効果を高めることができるか、日夜努力を重ねている。
- 研究室紹介
-
- 佐藤公子研究室
- 機械材料の中の代表的な金属材料に関する研究を行っている。その一つは金属を急熱した(例えば毎秒10,000℃の加熱速度)時の再結晶、拡散などの挙動を調べている。他の一つは加工に関する研究で、金属を切削切加工した場合の変形機構を、材料学的立場から調べている。
- 根岸秀明研究室
- 電磁成形法の学問的・技術的体系化を目指して、その成形機構の解明、成形技術の改善、各種塑性加工法への応用等の研究を進めており、これに関連して、成形型を使用せずに板材あるいは管材を任意の形状に成形することを目的としたタイレス加工法材料の高速変形特性、衝撃力を受ける構造物の変形と破壊について研究を行っている。
- 灰塚正次研究室
- 機械要素の中の重要な項目の一つである歯車に関して、スコーリングという表面損傷をテーマに、歯車の材質、表面処理、潤滑油、歯車の種類等を変えて、工学的立場からその一般的傾向を求めている。この分野の研究は工学上極めて小さい一つの領域であるが、機械工学のみならず物理学、金属工学等が複雑に関連し合つた表面工学の分野であるので、まだまだ未解決の部分が多く、油だらけになって実験を積み上げねばならない毎日である。
- 高木康成研究室
- 結晶の構造相転移の研究のうち、格子力学的立場から考察する理論-ソフトモード理論-の重要性により、われわれは直接ソフトモードが観察される光散乱分光、特にArレーザーを使ったラマン分光によって「相転移の動力学的な側面を種々の結晶 (KH2PO4, Gd2(M0O4)3, L1TaO3, Qvarts, etc) で調べている。更に、ソフトモードの振舞いは、固有周波数の変化だけでなく、そのラマン線形も大きく変わるので、その理論的考察も進めている。
- 通信機械コースの将来像
最近メカトロニクスという言葉が生み出されているように、機械技術と電子技術の融合は、今後の工業界において欠くべからざることであり、今後その必要性のますます大となることは、容易に想像される。本コースの目指すところはまさにそれであり、このような分野の技術者の活躍する場は今後も急速に広がるであろう。ところが「通信機械」という名称が、上記のような近代的なイメージと一致しないきらいがあるので、将来は世間にアピールするような名称にしたいと考えている。われわれの目的にピッタリした名称となれば、より多くの学生が集まるであろう。
- 学科紹介
4-3 電子工学科
- Ⅰ 電子工学コースの現状
-
- 学科紹介
電子工学科は1966年度(昭和41年度)に増設され、入学定員40名として発足した。その後、1968年度(昭和43年度)に入学定員が80名に増員されるとともに、電子工学(略称E)、情報処理(略称D)の2コース制で運用がなされている。
電子工学コースは、いわば時代の花形であり、数多くの入学希望者の中から選抜された優秀な勤労青年を対象とし、活発な教育が行われてきた。入学者の状況も多様化しており、企業や官庁において電子工学関係の専門職に携わる数年間の経験者、地方の工業高校を卒業して上京し、職場の理解のもとで勉学を志す新卒者などが代表的であるが、大学進学目標にして普通高校を卒業し、学部編入への希望を持ち続ける学生も少なくはない。
いずれにしても、昼働き、夜学ぶという厳しい条件のもとでの単位取得は並み大低ではなく、正規の3年間で卒業する学生は、およそ30パーセントである。
- カリキュラム
電子工学コースは、エレクトロニクスに関する中堅技術者の育成を目標としているが、専門教育の主体は、エレクトロニクス回路技術であり、電子応用技術者として必要な教育科目が用意されている。
入学すると、数学、物理、英語、体育などの一般教育科目と並行して、電磁気学、電気回路学、電子工学の専門基礎科目が開講される。1年次における必修科目のうち特定な14単位は、いわば関門であり、これを通過することが一つの試練なのであって、ここで足踏みをする学生も多い。2年次からは、電子回路学、電気測定学、固体電子工学、物性工学などとともに、物理実験、通信工学実験が開講される。この段階での基礎固めの目的で用意された電気理論演習は、個別に行われる講義内容を関連的に定着させるものであり、回路演習室の充実とともに本コースの大きな特徴となっている。3年次での専門科目には選択必修制がとられ、集積回路学、デジタル信号処理、パルス工学、自動制御などの電子応用的分野と、伝送回路網、電子機器学、マイクロ波工学、通信方式などの通信工学分野の中から、学生自らの意志に基づいて、必修科目が選ばれるようになっている。更に、情報処理教育が1年間を通して用意されており、いずれの分野にも普及している電子計算機に対処している。
担当教官は、教授1名、助教授2名、助手1名、技官1名の現員で構成され、電気回路学、集積回路学、電気理論演習、自動制御、デジタル信号処理など専門実験の各科目を担当している。主な研究分野は、UHF増幅器の雑音、マイクロ波及びミリ波伝送、電子素子の応用、マイクロコンピュータによる自動計測、情報と制御、海中テレメトリに関する研究などである。
- 電子工学コースの将来像
数年前まで短大随一の入学志願者のあった電子工学コースも、国立夜間短大に共通した入学者の低減現象に伴い、最近では志願者が減少する傾向を示している。これに対処すべく、入学試験方法の検討や改善がなされる一方、カリキュラムの充実、教育方法の改善などに日夜懸命な努力が続けられている。
しかしながら、電子工学という学問分野を夜間3年で修得させなければならないという時間、環境条件はあまりにも厳しい。一方、高校卒とともに自ら望んで勤労に従事し、あるいはそれを余儀なくされ、複雑高度化した社会の中で高等教育の必要性を痛感している青年の存在を無視することはもちろんできない。
したがって、過去十有余年にわたり国立機関として勤労者教育を実行してきた経験に基づき、更に拡張した形での高等教育機関への変貌が、併設短大における電子工学コースの将来像であるといえよう。
- 学科紹介
- Ⅱ 情報処理コースの現状
-
- 学科紹介
1966年度(昭和41年度)に電子工学科のコースとして設置された関係から、本コースの教科目は電子通信に関するものを基礎科目としている。コンピュータの機器の知識や利用技術に関する教科目は2、3年次に受講でき、特に、コンピュータを使用するプログラミング演習が週3時間の割合で設けられている。このうち、3年次には自主的に選定した課題についてグループ単位で完結させる演習がある。これは、この分野に必要なチームワークの訓練と、卒論に似た環境を与えるためである。関連知識として、システム工学、情報通信などを含む講義もこの時期に開講されている。演習を通じて、学生相互の対話や教官との接触も最近では多くなり、クラスの雰囲気も比較的あかるく、まとまりがある。なお、本コースには毎年女子の入学生が数名あり、時として男子学生を凌ぐ優秀な成績で卒業する者がある。
- カリキュラム
現在、情報処理コースに所属するスタッフは、鶴宏・木村耕・川西哲夫・岩岡聡一郎・田野中陽子の5名である。このうち、鶴宏教授は1978年度(昭和53年度)から本コースの主任を担当することになった。
初代主任の叶屋教授が1974年(昭和49年)に停年で退官され、松崎武夫教授(現在工学院大学教授)がその後の4年間を引き継がれたので、今は発足当初から数えて三代目にあたる。
鶴宏教授は本学へ移籍する前に、宇宙開発事業団で研究活動をしており、人工衛星、宇宙通信、あるいは、これらを含めた情報システムに造詣がある。教育面では、1年次の電子工学・3年次の情報処理システム工学の講義を担当している。
木村・川西両助教授は1969年(昭和44年)及び1974年(昭和49年)に電気通信学部より移ってきたが、ソフトウェア関連分野での研究、教育に豊富な経験を持ち、2年次・3年次の情報処理学と情報処理演習を等分に担当している。
岩岡聡一郎助手はコンピュータ関連機器のインターフェース等のハード・ソフト両面に堪能で、目下のところ画像処理の研究に従事するかたわら、プログラム演習等で学生に密着した指導を行っている。紅一点の田野中陽子事務官は、学生や教官のプログラムパンチ、コンピュータ操作を担当するほか、各種教材の作成に高度な技術を持ち、岩岡助手とともに本コースにとって不可欠な存在となっている。
なお、一般教養の丸山儀四郎教授には、本コースの学生のために数値解析の授業を担当していただくと同時に助言教官の役をお願いしている。また、非常勤講師として、電気通信学部の有山教授、工学院大学の柿沼教授に、それぞれ、情報処理学第三及び電子計算機工学の講義をお願いしている。
本コースには研究用機材として、ミニコンピュータ及びマイクロコンピュータ、これらを中心とした各種の入出力機器があり、これらを使用した研究成果が電子通信学会等に発表されている。
- 情報処理コースの将来像
コンピュータの技術と利用分野は今もなお驚異的に発展し続けている。したがって、この領域の教育体系も多岐にわたり、流動的な中堅技術者の育成を目的とする機関では、将来を予測するのは難しい。しかし、近い将来を目途とした2、3の準備は既に進行している。その一つは、学部に設置される情報処理教育センターや短大に導入された電子回路実験演習装置などの新しい施設を利用したプログラム演習である。第二は、1980年(昭和55年)代表的課題として、例えば、マイクロコンピュータの急激な進展に対処すべき教科内容の整備などである。第三は、本年度の入学生から、他学科の学生に対するコンピュータプログラムの演習を開講することである。これは、本コース以外の学生にも技術者として必須になりつつある情報処理教育を与えようとする時代的要請に応じたものである。
- 学科紹介
4-4 通信専攻科
短期大学部通信専攻科は1966年(昭和41年)4月、学生定員20名を以て発足した1年制の課程である。1978年(昭和53年)度末現在卒業者及び修了者の総数は135名である。
この専攻科の設置の目的は短期大学部電波通信学科、その他の学科または他の短期大学部を卒業した者が入学して1年の課程の履習によって第一級無線通信士の資格を取得することにある。
したがって、教授内容も短期大学部電波通信学科のものに比べて、より豊かな教養と、より高度な専門的なものとなっており、充実したものとなっている。専任教員の配置はなく、したがって、全般にわたって電波通信学科の教員が主導的な立場にあって教育等に当たっている。
専攻科の学生にはいっそうの勉学への意欲と気概及び専門的な無線従事者としての強固な意志を有する者が多い。それだけにこれからの無線通信に関する専門的教育への絶えざる配慮をする必要がある。