電気通信大学60年史
今日編1章 電気通信大学の現状
第2節:学部の現状
2-1 電波通信学科
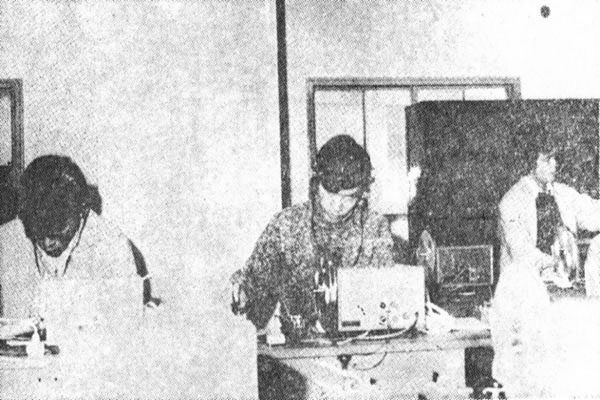
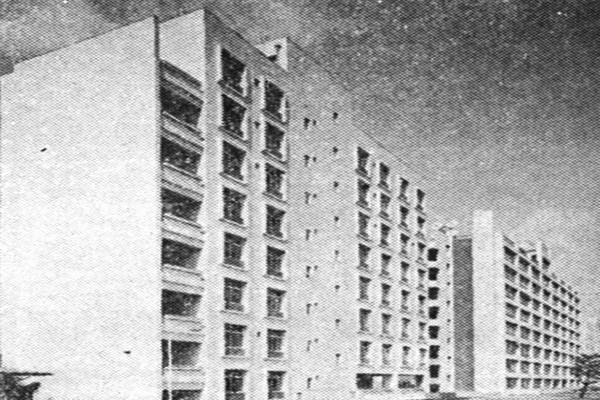
- (電波通信学科の現状)
-
- 学科紹介
電波通信学科は本学の前身からの伝統を最も色濃く受け継いでおり、一応本学のすべての学科の源泉となった学科とみて差し支えない。
現在この学科の学生定員は60名で、授業内容は、電磁気学、電気回路学、電子工学、電気測定学など電子通信工学の基礎科目のほか、純工学的な専門科目を十分に用意しており、この点からは一応他の電子通信系学科と異なるところは見当たらない。しかし他方当学科には通信の法的規制に関連して、法律学、社会学、国際関係方面の諸問題を取り扱う授業があり、一般の工業系諸大学、諸学科に類をみない。もともとこれらの授業は本学(全国でも)唯一の第一級無線通信士資格認定に必要なものとして取り上げられていたが、最近では広く情報と国際・社会・文化の諸問題を総合的に取り扱う立場から重視されるべきものと考えられている。
- 講座紹介
現在、電波通信学科は情報工学、航法工学、通信法規学、通信運用学、通信技術の5講座で編成され、共通専門の電磁気学講座が一体運営の形で参加している。
情報工学講座には、遠藤一郎教授、本多中二助手が所属しており、本学全般の情報工学方面の教育を担当するインター・デパートメント的な講座となっている。現在、宇宙通信、国際計算機網、通信理論、システム工学方面の研究を行つている。
航法工学講座には、荒川輝明教授、岩倉博助教授、宮武貞夫助手が所属している。この講座は当方面の日本唯一の講座で、現在・航法工学、電気回路学などの授業を担当し、マイクロ波工学、伝送工学、プラズマ工学方面の研究を行っている。
通信法規学講座には、合田周平教授、小菅敏夫助教授、秋山登助手、上田美智子事務官が所属している。この講座も本邦唯一のもので内容的にも他に類をみない。現在、国内外通信法規、国際法、行政法などの授業を担当し、社会システム、通信法規、国際法などの研究を行っている。
通信運用学講座には、望月仁教授、三橋渉助手がおり、通信運用学関係の授業の世話のほか、電磁気学、電子工学などの授業を担当し、船舶通信の自動化、光波の伝搬、海洋エネルギーなどの研究を行っている。
通信技術講座には、田中正智講師、有澤豊志、足立登両技官が所属している。この講座は通信の送受の理論と演習についての授業を担当しており、本学中最も多忙な講座の一つである。通信教育CAI、宇宙通信、リモートセンシングなどの研究を行っている。
共通専門所属の電磁気学講座には、御牧義助教授、武田光夫講師、田辺正実助手、和田文夫技官が所属している。この講座は本学の電磁気学の講義の総括的な世話をしており、現在、電磁気学のほか、情報処理論、電子・電気回路学等の授業を担当している。雑音解析、光学情報関係の研究が行われている。
- 学科紹介
- (電波通信学科の将来像)
-
先に、当学科が本学最古の伝統を受け継いでいることを述べたが、これは多くの伝統ある機関と同様に、当学科が古い形態のままに止まっていることを意味しない。
現在まで引き続き船舶通信の諸問題を取り扱いながら、常にその基礎に横たわる諸科学に着目し、その時代時代の学術と文化の中に、個々の諸問題の占める立場を見定めながら発展してきた。このような姿勢は当学科が現に取り上げている授業内容あるいは研究内容のいずれもが時代の最先端をゆくものであることからも明確にうかがえると思う。
今後も当学科のこのような姿勢は変わることなく、電子通信方面のみならず、本学科に独特な法規、国際関係、情報文化、人間行動などを含む情報・システム工学的側面を拡充し、今後も多方面にわたって本学発展の源泉となっていくものと考えられる。
2-2 通信工学科

- (通信工学科の現状)
-
- 学科紹介
本学科は大学創立に当たり陸上通信専攻として発足し、ついで電波通信学科陸上通信専攻となり、1966年度(昭和41年度)に現在の通信工学科に改組した学科である。創立以来の古い歴史をもち、当初はその名の示すごとく有線関係の教育を主としたが、科学技術の進歩とともに急速に発展し、一般教育科目の基盤の上に立って、エレクトロニクスや電気通信などの基礎になる電磁気学、電気回路学、電子回路学、電気測定学などをはじめとする専門基礎科目を修めることはもちろんのこと、更に電子工学の全分野にわたる幅広い技術者や研究者の養成のために、その中心となる情報伝送、電子交換、電気音響、電子デバイスなどの各分野を学習できるように構成されている。また基礎になるデータ伝送、システム工学、情報処理を軸にコンピューター、回路と場の理論、パルス工学、マイクロ波、レーザなどのほか集積回路、半導体工学、極低温工学、オートマンなどの学問も習得できるようになっている。
- 講座紹介
本学科は入学定員60名、高専特別編入定員10名。下記の6講座で編成され、また実験工学講座(共通講座)の協力を得ている。教育担当スタッフ及び現在の担当授業科目を列記すると
電気回路学講座 スタッフ 石坂謙三教授、樺澤康夫助教授 授業科目 電気回路学及び演習、演算工学、工学実験第二(動インピーダンス及ぴ動アドミッタンス) 伝送工学講座 スタッフ 相田義一教授、横田誠講師、小河原博信助手 授業科目 電気測定学、伝送理論、伝送工学、伝送回路、位相回路網、工学実験第二(フィルタ) 搬送工学講座 スタッフ 山中惣之助教授、後藤俊成助教授、宇佐美興一助手 授業課目 電磁気学第一及び演習、搬送工学、伝送方式論、パルス工学、集積回路工学、工学実験第二(パルス通信) 交換工学講座 スタッフ 雁部頴一教授、富田悦次助教授、藤橋忠悟助手 授業課目 交換工学、組織工学、論理回路学、演算工学、計算機演習 音響工学講座 スタッフ 山口善司教授、岸憲史助教授、黒沢明助手 授業課目 電気音響学、電子回路学及び演習、工学実験第二(相互校正法) 電子部品学講座 スタッフ 岡本孝太郎助教授、小形考角助手 授業科目 固体電子工学、工業実験第二(MOSコンデンサ) 実験工学講座 スタッフ 武井健三教授、田中清臣助教授、桑田正行助手、高橋泰行助手 授業科目 工学実験第一(直流電差計、磁気測定、オシログラフ、トランジスタ増幅器と発振器など)
- 学科紹介
- (通信工学科の将来像)
-
本学科の性格上、情報伝送、情報処理、情報交換、これらを支える新しい電子デバイスなどに関する高度な教育が必要であるが、 現今の目覚ましい技術革新及び学際領域の問題など、その分野はますます専門細分化されて行く傾向にある。 しかし、4年間の学習時間には制限があり、卒業後の活動分野、技術の進歩などを考えるとき、 細分化された教育の有効性はあまり期待できない。そこで専門知識の詰め込みでなく、問題の把握、調査、分析、 解決へのアプローチの方法、システマチックな遂行能力の涵養の機会も多くつくりたい。
2-3 応用電子工学科

- (応用電子工学科の現状)
-
- 学科紹介
応用電子工学科は本学電気通信学部が設立されたときの電波工学専攻を引き継いだもので、電波工学科から1966年(昭和41年)に現学科名に名称変更したものである。
設立当初は技術系分野は電波工学専攻だけであったが、その後「学科」となるとともに多くの学科ができ、現在では電波通信学科、通信工学科、電子工学科とともに電気系四学科の一つとなっている。
応用電子工学科はエレクトロニクスの基盤から各種の応用分野を目指した研究と学生の養成に努めており、電子・通信工学、電波工学、情報工学などの基礎理論から実用化まで幅広い研究と教育とを行っている。したがって、本学科の卒業生は官公庁、メーカー、マスメディア関係をはじめ、教育、金融、サービスなど第二次、第三次産業の全分野にわたって活躍している。
- 講座紹介
応用電子工学科は(編成順に)電気測定学・電波工学・電子機器学・電子応用工学・電波物理学の5講座と共通講座の通信基礎学の計6講座で構成されている。これらの講座の主な研究項目と受け持っている主な授業科目は次のようである。
電気測定学講座はレーダシステム、電子航行システム、医用電子、生体エレクトロニクス、リモートセンシングなどの研究をしており、講義としては電気測定学を受け持っている。
電波工学講座はレーザ光のマイクロ波変調と検出、光ファイバー中の電磁波伝搬、IC中の温度分布、マイクロ波集積回路などの研究をしており、電磁界解析をμ波回路や光回路に応用した成果を挙げている。分担している主な授業科目は超高周波工学である。
電子機器学講座はコンピュータネットワーク、コンピュータシステムと周辺装置、学習認識システム、位相同期ループなどの研究をしており、Dネットと呼ばれる学内コンピュータネツトワークの形成に大きな役割を果たしている。また、タイ国との国際ネットワークも計画している。分担している主な授業科目は電子回路学、データ伝送学である。
電子応用工学講座はグラファイト、太陽電池、イオン注入物理などの研究をしており、新しい固体デバイスの開発、新しいエネルギー学の探求に意欲を燃やしている。分担している主な授業科目は電磁気学である。
電波物理学講座はVLFプラズマの波動の地球磁気圏伝搬、人工衛星による超高層大気物理、木星電波、大気重力波などの研究をしており、菅平宇宙電波観測所と一体になって高層物理の研究に取り組んでいる。また、この講座からは現在までに4名の南極越冬観測隊員を出しており、芳野教授は第2次と第18次に参加して、後者では越冬隊長の重責を果たしている。分担している主な授業科目は電磁波伝送論、プラズマ工学である。
通信基礎学は共通講座であるが応用電子工学と完全に一体運営している。ここでは弾性衝撃波の発生と検出、音響変換器のエネルギー変換などの研究をしており、電気系と機械系とのエネルギー交換の分野に大きな足跡を残している。分担している主な授業科目は電気回路学である。
応用電子工学科には本学出身者が多く活躍しており、現在教授4名、講師1名、助手2名が奉職していて、教官の半数を占めている。
- 学科紹介
- (応用電子工学科の将来像)
-
応用電子工学科は本学設立時の工学系分野を継承したものであるが、本学が初期の電気通信の分野から時代の趨勢を踏まえて発展する中で電気系学科の一つとして位置付けられてきた。そして電子工学、情報工学の発達の中で、物性、回路、システムから地球物理までの広いエレクトロニクスに目を向けている。
電子計算機の発達は多量のデータ処理を短時間で可能にしたので各講座での実験データ解析データはすべて計算機処理され、また、ネットワークが完成すれば、どこからでも大型計算機にアクセスできる態勢が整えられる。
また、レーザ及び光ファイバーの発展は新しい光電子工学を生んでいる。光はこれまでのμ波と比べても数けた高い周波数であるから、従来より格段に多い情報を得ることができる。光を従来の電磁波と同様に使えるようにするのが将来の一方途である。
2-4 電子工学科

- (電子工学科の現状)
-
- 学科紹介
1959年(昭和34年)の本学開設以来、最初の新設学科として設置され、以来、着実な歩みを続け、受験者数、求人数も多く本学電気系の中核的役割を演じて今日に至っている。本学科はエレクトロニクスに関する基礎から応用に至る広い範囲にわたる教育を実施するとともに、所属する教官の研究も多岐にわたる。学生に対しては、一般教育科目のほか、エレクトロニクスの基礎となる電磁気学、電気回路学をはじめとする専門基礎科目を重点的に教育し、更に、物性、回路、システム等の各分野の専門講義が履修できるようになっている。研究面では、物性、量子工学から音響、画像、情報処理、制御工学に至るまで幅広く扱っており、その成果は選択科目、卒業研究、輪講を通じて教育面に生かされている。
- 講座紹介
電子工学科は電子物理学、電子装置工学、半導体工学、電子回路学、制御工学の5講座と、共通講座に所属する電力工学講座が学内運営上電子工学科内の講座として扱われているので6講座よりなる。
電子物理学講座は角田稔教授、中田良平助教授、河野勝泰助手からなり、角田教授は、半導体を中心として固体の電子物性について講義する「固体電子工学」を受け持ち、中田助教授は、電子工学、材料物性に必要な基礎的物性論を講義する「固体論」を受け持つ。
電子装置工学講座は、昭和54年度には従来の電子管工学講座を改称する予定で、長谷川伸教授、岩下正雄講師、佐野敏一助手からなる。長谷川教授は電気系四学科必修とされている「基礎電子工学」と、固体素子では置き換え難い電子管を中心とした「電子管工学」を受け持ち、岩下講師は「電気回路学」と「同演習」を受け持っている。
半導体工学講座は木原太郎教授、安永均助教授、奥山直樹助手よりなり、木原教授は「量子物理学」を、安永助教授は電気系学生にとって最も基本となる「電磁気学」及び「同演習」を受け持っている。
電子回路学講座は岡村史良教授、氏原紀公雄助教授、青山彦聖助手よりなり、岡村教授は、アナログからデジタルまで、トランジスタからICに至る広範囲の「電子回路学」を、氏原助教授はレーザーを中心とした「量子工学」を受け持っている。
制御工学講座は遠藤耕喜教授、新谷治生助教授、篠田正信助手よりなり、遠藤教授、新谷助教授の両者で全学の学生を対象とした「自動制御論」を受け持っている。
電力工学講座は熊本芳朗教授(併)、新谷治生助教授(併)、小松光男助手からなり、この講座の持ち講義である「エネルギー変換工学」は現在遠藤耕喜教授が受け持っている。
- 学科紹介
- (電子工学科の将来像)
-
エレクトロニクスの分野の目覚ましい進展に対応し、本学科がどのように変換して行くべきかについては、軽々しく即断はできない。しかし、本学科の学生に与えるべき必要知識も極めて多岐多様に渡らざるを得ない状況にある。大学においては、学生に対して単に覚えさせるということの外に、考えさせることも必要であり、過度のカリキュラムを課して、単なる詰め込み教育を行うという形は避けなければならない。したがって、大学教育で何を教えるべきかということは、古くて新しい問題であり、本学科でも機会あるごとに、これを議論している。現在では、演習を課しながら基礎科目に時間をかけるという形のカリキュラムに転換していく事が、社会の多様な二ーズに対応する手段なのではあるまいかという意見が多い。
2-5 経営工学科
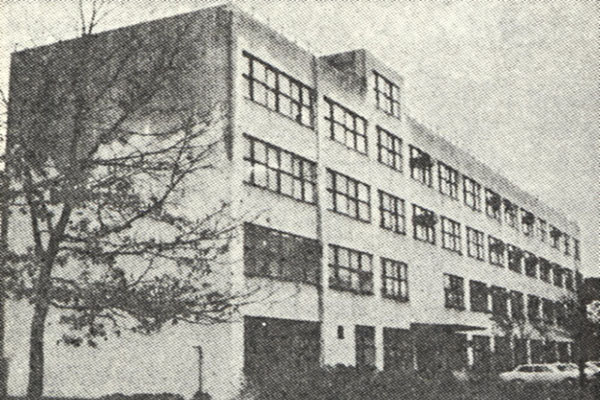
- (経営工学科の現状)
-
- 学科紹介
経営工学科は一言でいえば、企業経営に発生する諸問題を工学的思考、手法によって解答を求め、更にこれを経営的思考に導くことの出来る人材の教育を目的とする学科である。もちろん、経営活動にかかわる問題は、多くの複雑な要因を含み単純なものではない。その意味では要因を定量的・定性的に把握するだけでなく要因相互の関連性をも個別的・全体的に理解することができなければ、問題の解答者たり得ない。しかし教育上限界があるので、すべてを網羅することは出来ない。
そこで本学の経営工学科が他大学の経営工学科と異なる大きな特質は、技術者としての専門科目として、電磁気学、電気回路学、電子回路学を必修としている点である。企業経営において必要なことは、技術者の話が分かり、事務家の要請が理解出来る人材の存在である。更に経営の多元化に伴う多変量解析のテクニックをコンピュータの利用とともに習得させる経営管理者の教育を性格づけている。
- 講座紹介
経営工学科は次の5講座をとっている。
- 基礎経営学講座
-
企業周辺から企業経営を規制する関連科目として、企業法・経営学・会計学・社会学・政治学的アプローチを通して、企業経営の基礎を理解せしめる。君塚芳郎教授、布施博正助手によって経営分析・会計史・企業形態論・公企業論の研究がなされている。
- 産業経営学講座
-
企業経営活動における基本的要因、特に人間労働の心理学的・生理学的研究を内容とし、他方経営活動のシステム的研究がなされている。臼居利明教授、萩野剛二郎助教授、坂本和義助手がスタッフで、研究室では産業適性の実験的研究、マン.マシンのシステム研究、制御理論、動的システムの状態推定システム理論の研究がなされている。
- 企業管理学講座
-
マネジメント論の総論、各論を内容とする経営管理・経営組織・生産管理・実験計画法などが開講される。大須賀政夫教授、狩野紀昭助教授、神品弘光助手の研究室では研究開発管理、経営目的の多様化の多変量解析の研究、システム分析、信頼性データの解析、在庫システムの解析などの研究がなされている。
- 計数管理学講座
-
企業経営活動を全体的・部分的に計数的尺度によって管理しようとするものである。経営意志決定論、品質管理、価値分析・経済工学、作業管理などが内容とされている。河村良吉教授・荻原洋太郎助教授、若尾良男助手の各研究室では、統計数学的管理手法の研究、価値工学的分析、作業動作の解析などの研究が進められている。
- 情報管理学講座
-
経営情報の収集と意志決定のための解析がねらいとされる。内容としてはオペレーショシズ・リサーチを中心として経営統計・マーケッティングなどがある。鍋島一郎教授、松山敬左助教授、丸山茂子助手の各研究室では、スケジューリング理論、組合せ計画法、動的計画法、大規模システムに対する発見的算法、システム・プログラム等の研究が行われている。
- 学科紹介
- (経営工学科の将来像)
-
社会環境の変化に伴い、隣接諸科学が次々に誕生し、類似の学科も少なくない。その中にあってわが大学の経営工学科が、独自の性格のもとに、社会的ニーズに即応した人材の教育を確立して行かなければならない。
その独自の性格とは、経営におけるマネジメントの問題解決者の教育である。しかも近代的解析手法の習得と、コンピュータの解析力を活用することにより、ますます複雑化する経営活動のシステム的把握を学習で体得せしめる必要がある。
電子工学の技術者と対話が出来、管理上の問題に解答を与えることの出来る人材の育成であるとともに、単なる問題解答者に止まるものではない。経営は主体的実践行動を内容とするものであるから、経営の社会的責任を果たす行動、福祉社会を創造する新しい時代の経営行動への解決者の育成でなければならない。
2-6 機械工学科
2-7 機械工学第二学科
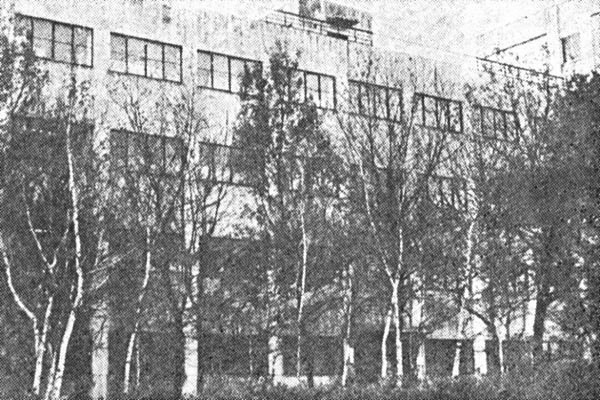
- (機械工学科及び機械工学第二学科の現状)
-
- 学科紹介
機械工学科は1960年度(昭和35年度)に通信機械工学科として設置され、1966年度(昭和41年度)に機械工学科に改称された。また機械工学第二学科は、時代の要求に応じて1974年度(昭和49年度)に設置された。それ以来二つの学科は広範な機械工学の諸分野を相互に補い合う形で一体となって教育と研究を遂行している。
両学科は組織の上で区別されるものの一体運営の原則を貫いており、研究費の配分から教育まで窓口をほぼ一つに統一している。学内では二学科を合わせて機械工学系学科と称している。
- 講座紹介
両学科を構成する講座及び両学科に共通する授業科目を紹介すると次のようになる。
機械工学科 機械要素講座 教授 成瀬長太郎 講師 石川晴雄 助手 根本良三 機械工作法講座 教授 鈴木秀雄 助教授 横内康人 助手 村田真 弾性及び塑性 教授 田中栄 講師 秋田敏 助手 高松徹 熱流工学講座 助教授 内田豊 助手 小泉博義 固体力学講座 教授 皆川七郎 講師 本間恭二 助手山田實 機械工学第二学科 機械力学講座 教授 石井友次 助教授 石川鈴枝 助手清水弘幸 機械材料講座 教授 市川昌弘 助教授 酒井拓 助手 大橋正幸 自動機械学講座 教授 石川二郎 助教授 梶谷誠 助手益田正 信頼性工学講座 教授 佐々木茂美 講師 越智保雄 なお、機械工学系学科は、前節に紹介された共通講座の中の流体工学講座と親密な協力関係を保っている。
流体工学講座 助教授 黒田成昭
また、付属の実験実習工場は教育ばかりでなく、全学の研究に実験装置の試作等を通して寄与している。
- 専門授業科目
-
- (必修科目)
- 材料力学、機構学、機械工作、機械設計、振動工学、機械材料・熱工学、流体工学、機械工学実験、電気工学実験、機械製図、機械設計製図、工作実習、輪講、卒業研究
- (選択科目)
- 関数論、代数学、応用解析学、応用代数学、統計数学、解析力学・原子物理学、化学特論、電磁気学、回路論、計測工学、弾性力学、塑性工学、電気音響学、非線形振動論、信頼性工学、生産システム工学、情報機械工学、機械工学演習、電子工学、電子回路学、応用電子計測・エネルギー変換工学、電子部品論、自動制御論、演算工学、経営工学
- 学科紹介
- (機械工学科及び機械工学第二学科の将来像)
-
現在、世界は深刻な諸問題に直面しており、人類の未来は、科学者や技術者の英知と創意にかかっていると言っても過言ではない。とくに、わが国の産業は、省資源・省エネルギー・無公害かつ高附加価値産業への質的転換を迫られており、このような新しいニーズを充足させる製品や生産技術の開発には機械工学が重要な役割を担っている。しかも、要求される技術はますます複雑高度となり、もはや従来の狭い分野の専門技術だけでは対処しきれず、広い視野に立った新しい発想と総合力を必要としている。とくに、最近のマイクロコンピュータに代表される情報関連技術の革命は機械技術の分野にも大きな影響を及ぽしつつある。本学機械工学系学科は、将来も、実体のある機械システムを作りあげるという本来の機械工学を根幹にしつつ、エレクトロニクスやコンピュータを機械要素の一部とみなすことができ、機械・電子・ソフトの一体化による高度な知識集約産業に貢献し得る創造性に富んだ新しいタイプの機械技術者の養成を目指している。
2-8 材料科学科
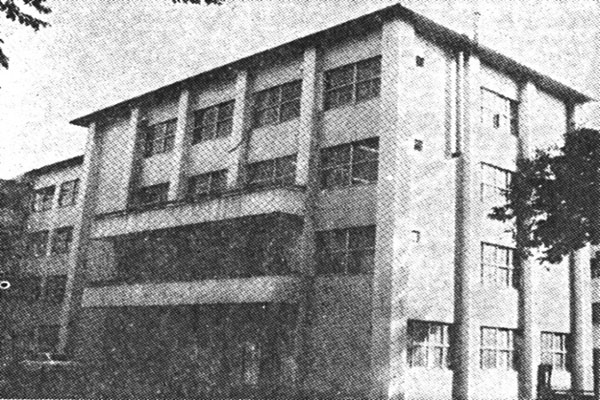
- (材料科学科の現状)
-
- 学科紹介
材料科学科は、1964年度(昭和39年度)に創設された通信材料工学科の拡充発展により1969年度(昭和44年度)に生まれた新しい学科である。
電子・電気工学または通信工学に限らず、広く工学の領域で扱われる物質、すなわち"材料"の重要性という点から、材料科学科では、物質の特性に関する基礎的な学問を教授し、学生が学術に親しむとともに、更に、基礎より応用へと意欲的に学問・技術もさせて行く能力の養成に努めている。
しかし、材料の研究・開発は、極めて多方面の分野にわたることであるので、当学科の規模ですべての領域を包含することは不可能であり、また賢明な策ではない。そこで、当材料科学科では、エレクトロニクス及びこれと関連した分野での材料を念頭に置いて、しかも基礎的な物性面の教育に力を入れている。物理化学、有機高分子化学、量子論、固体物理学、電磁気学、電気回路学及び関連する実験・演習が、教育の主体となっている。換言すれば、物理工学的な色彩を持たせると言っても良いだろう。
- 講座紹介
材料科学科は、次の5講座で構成されている。
材料物性学講座 教授(兼任) 井早康正 助教授 佐野瑞香 助手 鈴木沖 助手 伊藤博敏 材料分析学講座 教授 藍原有敬 助教授 岩崎不二子 助手 林茂雄 誘電材料学講座 教授 丸竹正一 助教授 丸山信義 助手 佐々木行彦 磁性材料学講座 教授 神戸謙次郎 助教授 伊里武男 助手 橋本満 高分子材料学講座 教授 大橋守 講師 辻本和雄 助手 山田修三 なお、このほか、講義担当の非常勤講師として、今井勇(東京大学)、鐸木啓三(筑波大学)、永田一清(東京工業大学)、菱山幸宥(武蔵工業大学)、三川礼(大阪大学)、遠藤慶三(東京都立大学)
- 学科紹介
- (材料科学科の将来像)
-
理想あるいは希望の将来像と現実的な可能性を踏まえた将来像とでは、大きな差異があることは認めざるを得ないが、あえて、理想像を描くとすれば、次のようなものとなろう。
- 物性物理学、化学、金属学、電子・電気材料学をすべて包含した従来の学科構成にとらわれない新しい構想の組織として発展すること。
- 学部学生の定員を減らし、大学院学生の定員を増やして、材料の基礎研究と、新しい材料の開発研究に重点を置くようにする。すなわち、従来からある学問の分類にとらわれることなく、これからの学問研究のあり方として、各領域を結びつける学際的な色彩を強く打ち出して行くことが必要であろう。
2-9 物理工学科
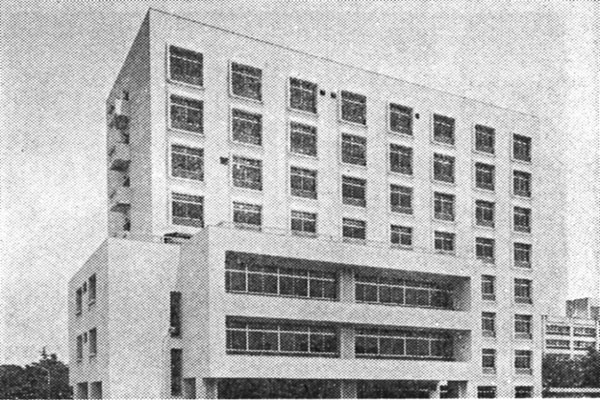
- (物理工学科の現状)
-
- 学科紹介
1967年度(昭和42年度)に設置されたこの学科は、電気通信学部の中にあってその特徴を生かす一方、物理的色彩も兼ね備えているのである。近年における物性物理学の進歩は目をみはらせるものがあり、その工学への応用は人類の日常生活を一変させたと言っても過言ではない。その功罪をよくわきまえ、物理学に根差す新しい工学を育成する力を備えた人材を育てることを目指している。教授、助教授ばかりでなく助手も、研究者として有能な人物がそろい、全員で教育に参画している。
- 講座紹介
この学科は、固体物理学、分子工学、放射線工学及び量子光学の4講座で編成され、共通講座流体工学の教授にも参加していただいている。
前記講座の教授、助教授により、古典物理学の柱である電磁気学、解析力学、近代物理学への導入として原子物理学、物理学を学ぶための基礎として物理数学、古典物理学と近代の量子物理学との両方に関連する統計物理学、近代物理学の中心である量子力学の諸講義が必修、準必修科目として開設されている一方、助手、非常勤講師の参加を得て物理工学演習、電子計算機入門、物理工学実験の諸科目を必修として設け、学生に自ら問題を解く基礎力をつけ、電子計算機の利用及び実験機器の取り扱いに慣れさせるべく力を注いでいる。
学部教育の総仕上げとして輪講及び卒業研究を必修科目として設け、少人数での討論を通じて、実験的あるいは理論的な問題に直面した場合にそれを自ら処理できるための修練を積ませている。
また、上記の専任スタッフのほか、本学の他の学科の教授、助教授、講師及び非常勤講師として東京大学、東京工業大学、東京都立大学などから出講していただいている先生方により電気測定学、電子・電気回路学、自動制御論、情報処理論、原子力工学、応用原子核論、放射線効果論、放射線生物学、生物物理学、高分子物理学、固体物理学、磁性体論、半導体物性、低温物性、機器分析学、応用工学など多彩な科目が選択科目として開かれているほか、専任のスタッフにより連続体力学、電算機応用及び演習、物理工学汎論、物理工学各論がやはり選択科目として講義されている。そのほかに量子力学や電磁気学のアドバンスト・コースもあり、学生の多様な興味にこたえている。
- 学科紹介
- (物理工学科の将来像)
-
この学科のカリキュラムは、1973年度(昭和48年度)に情報数理工学科が誕生した際に大綱が決められ、何度かの小修正を経て現行のようになったものであり、近代物理学の基礎を十二分に固めさせる心づもりのもとに作られたものである。このカリキュラム自身が欠陥を持っているとは考えないが、しかし、絶えず変動する社会情勢に伴って入学してくる若者の気質も変化して来ていることを考えると、いつまでも現行のままでよいというわけでもない。電気通信関係の諸学科、情報科学関係の諸学科の間にある本学科の環境をいっそう積極的に生かし、物理学に基礎を置いた情報科学の教育を現行よりも強化することが適切であろうと考えられる。ただし、物理学的基礎そのものに興味を抱く学生を失望させることがあってはならない。この辺りを十分検討した上で、上記のような方向に進むべきではないかと考える。
2-10 計算機科学科
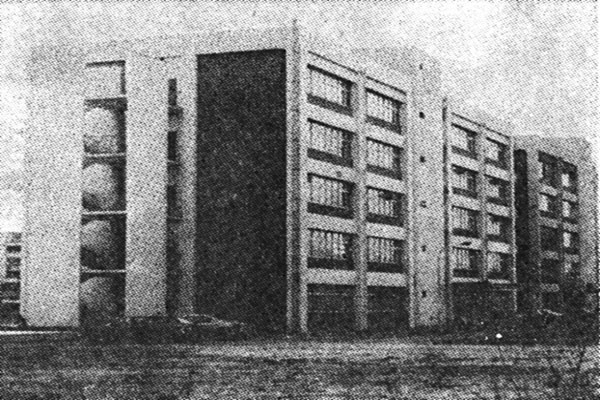
- (計算機科学科の現状)
-
- 学科紹介
計算機科学科は、1970年度(昭和45年度)に電子計算機学科の名称で設置され、1977年度(昭和52年度)より計算機科学科と改称したものである。
改めて記すまでもなく、昭和40年代に入ってわが国においても計算機の普及は著しく社会のあらゆる分野で広く利用されるようになった。これに伴って計算機技術者あるいは情報処理技術者の育成が急務となり、これに対する国家的施策の一つとして昭和45年度以降、国立大学の理工系学部に情報関連の専門学科が重点的に新設された。当学科はその第一陣として、東工大・山梨大・京大・阪大の類縁の学科と同時に設置された。
計算機は、今世紀後半に入って急速に発展した情報科学・情報工学の主要な柱の一つであり、また今日の情報化社会の基盤でもある。
計算機科学はこの計算機のソフトウェア・ハードウェアそのものについて、またその応用の基礎に関して、理論の面並びに実践の面から研究する新しい学問領域であって、今日もなお急速に進歩・発展を続けており、活気と魅力に満ちあふれている。
当学科は計算機科学の研究、教授を通じて計算機のソフトウェア・ハードウェアの開発・設計に当たる高度の専門技術者、情報処理の専門技術者、あるいはこれらの基礎を研究する研究者を育成することを主たる目標とするものである。計算機技術の進歩は極めて早く、その応用範囲も急速に拡大しつつあるので、この分野の技術者・研究者は単に最新の技術・理論を修得するのみならず、しっかりした基礎学力の上に柔軟な思考力と適応性を持つことを特に強く要求される。したがって、カリキュラムは実験・実習に重点を置くとともに、基礎も重視し、またソフトウェア・ハードウェア・理論の三つの面で均衡のとれた専門教育が行われるように配慮して作られている。
当学科は前記のとおりにこの種の学科の中では最も早い時期に創設されたことと、特に計算機そのものに焦点を強く絞った性格を打ち出してきたことによって、特色ある学科として注目されている。
- 講座紹介
現在、論理回路設計学・記憶装置学・ソフトウェア基礎学・システムプログラミング学・端末装置の5講座で編成されており、また、教育用計算機室が付置されている。
各講座の研究内容は次のとおりである。なお、これらの講座の名称は計算機科学の現状と将来の姿に必ずしも適合していないので、名称変更を検討中であることを申し添えておく。
- 論理回路設計学講座
- 計算機制御方式、計算機応用システム、プログラミング言語とコンパイラ、アルゴリズム解析、プログラミング方法論。
- 記憶装置学講座
- バブル磁区デバイス、バブル磁区材料の研究、磁壁移動の数値解析、計算機を使った磁気測定。
- ソフトウェア基礎学講座
- 多重通信路の情報理論、多重通信路の符号理論、確率過程とその処理、統計現象の計算機処理、人工知能、プログラムの自動合成、プログラムの理論、計算の理論、オートマトンと言語の理論、スイッチング理論。
- システムプログラミング学講座
- オペレーティング・システム、計算機システムの性能解析、ソフトウェアの信頼性、数学的ソフトウェア、応用プログラム、ロボット。
- 端末装置学講座
- 装置設計の基礎及び共通的手法、計算機の自動設計、計算機システム、計算機ハードウェア一般、図形処理。
- 学科紹介
- (計算機科学科の将来像)
-
当学科は1978年(昭和53年)3月までに創設以来5回の卒業生を社会に送っているが、その大部分は計算機メーカー、ソフトウェアハウス等、情報産業の中心的な職場で活躍している。官公庁や一般の企業の情報処理部門に就職する者も多い。また、教職に就く者、大学院へ入学する者も少なくない。
計算機はなお引き続き進歩を続け、基礎科学の研究・技術開発・その他あらゆる種類の産業の中で不可欠のツールとして用いられるのみならず、社会生活全般更には家庭・個人の日常生活の中にまで広く深く浸透する大勢にある。基礎研究の面においても人材育成の面においても、当学科に課せられた使命は重い。今後いっそうの発展を念願しつつ、研究・教育の充実をはかるべく努力しているしだいである。
2-11 情報数理工学科

- (情報数理工学科の現状)
-
- 学科紹介
情報系の学科は近年数多く設立されたが、その中でわが情報数理工学科は、数学の基礎を重視しているユニークな存在である。群、環、体などの代数系の概念は情報理論、組合せ論、実験計画法などに不可欠な道具であり、数値計画による問題処理は理工学における基本的方法論である。現象を記述する数学モデルの構成、数学モデルの解析的研究、離散系の数値計算、現象の理解と数学モデルの妥当性の検討という体系を具体化し、工学的応用能力をも身に付けた人材を養成することを目標としている。学科専用のコンピュータを有し、演習、実験、実習を通じて理論と実際との結合が会得できるように教育する。
この学科の出身者は数学理論に強い興味をもつものから、高度のソフトウェアの実際面に堪能なものまで極めて多様性に富んでおり、それがこの学科の一つの特徴でもある。卒業生の数はまだ多くはないが、情報処理関係だけでなく、電機、機械等各種製造業、商社、金融、運輸、通信、出版、官公庁、公団、その他の広い分野に進むものも少なくない。
- 講座紹介
本学科は4講座編成で、講座名と教官は次のようになっている。
応用解析学講座 教授 水野弘文 助教授 渡辺二郎 数値解析学講座 教授 林一道 助教授 牛島照夫 情報基礎学講座 教授 助教授 名取亮 計画数学講座 教授 森口繁一 助教授 小林光男 主要授業科目 担当者 内容 情報代数原論 水野弘文 代数系の基礎概念 算法原論 小林光夫 プログラミングの基本概念 情報数理工学原論 A 渡辺二郎 極限、収束、完備性など解析学の基本 情報数理工学原論 B 林一道 ルベーグ積分の初歩、確率や物理数学への応用なども含む 情報数理工学原論 C 渡辺二郎 常微分方程式系の解の一意性、安定性 関数解析学 牛島照夫 ヒルベルト空問、線形作用素、超関数 数値解析学 名取亮 線形計算、関数近似、数値積分 確率統計 藤沢武久 確率論の基礎とその近代統計学への応用 計画数学 森口繁一 計画の立案、評価、最適化などの手法、数理モデルの作成と検証、シミュレーション手法 代数・幾何 A、B 水野弘文 代数曲線をモデルとして代数的手法を学び、更に閉リーマン面の古典理論を学ぶ。 情報数理工学実験
第一、第二、第三全教官 基礎的実験技法の習得から始め、数値計算(乱数、常微分方程式、偏微分方程式、連立一次方程式、固有値)、レーザーの情報処理への応用などに及ぶ。 その他に、より高度の内容の講義として、情報数理工学各論 A~Fなどがある。
- 学科紹介
- (情報数理工学科の将来像)
-
この学科はこれからも数学を基礎として進むべきであると考える。しかし、純粋数学だけに片寄ってはならないし、またコンピュータ一辺倒になってもいけない。確固とした数学的基礎を身に付けた上で、情報科学、数理工学、情報工学の諸分野において活躍し得る人材を養成することを目指すべきである。いわゆる情報化時代の風潮に押し流されるのではなく、時代の要請を先取りするだけの柔軟性と生命力にみちあふれた学科として今後いっそう発展して行くことを信じている。