電気通信大学60年史
前編序章 無線通信のめざめ
第3節 無線電信の実用化
マルコーニが電波式無線電信発明に成功した翌1897年(明治30年)10月、逓信省は電気試験所の松代松之助電信係主任技師に命じて技術的研究に着手した。マルコーニの発明は画期的なものであり、かつ理論的にも技術的にも秘密に付されていた関係で参考資料に乏しく、研究は非常に困難であったが、研究部員はあらゆる困難を乗り越えて着々と成果を挙げ、実用通信に適するところまで漕ぎつけた。
実用通信を行うにあたって法規を必要とするのは当然である。逓信省は1900年(明治33年)10月10日、逓信省令第77号で
電信法は第2条、第3条、第28条及第43条を除くの外之を無線電信に準用す
を公布した。初期の逓信省の見解では、電波の特性上、通信の秘密は機械的に防止する方法がなく、公衆通信を妨げるものだから当分は私設を全然認めない方針であった。
無線電信の初期、マルコーニは、世界中の船舶と要所々々に海岸局を設け、これにマルコーニ会社製の無線電信を装置し、その無線局は他の会社製の無線電信を装置した無線局とは交信させないという事業独占の野望を抱いていた。ドイツ政府はこれに対抗して、電波の共有・無線電信の普遍性・製造の自由を主張して、1903年(明治36年)8月ベルリンで国際無線電信予備会議を開いた後、1906年(明治39年)10月ベルリンで第1回国際無線電信会議が開催されて、国際無線電信条約並びに附属業務規則が締結され参加27カ国がこれに調印した。この条約は1908年(明治41年)7月1日実施されており、逓信省は約3カ月さかのぼった同年4月に無線電報規則及び無線電報取扱規程を制定している。そして同年6月にベルリンで締結した国際無線通信条約及び同条約附属業務規則を公布し、同月外国無線電報規則及び外国無線電報取扱規定を制定した。
1908年(明治41年)5月、銚子ほか三つの無線海岸局及び天洋丸ほか6隻に無線電信局を開設して無線電信による公衆通信の取り扱いが開始され、長い間待望されていた逓信省における無線電信の実用化が果たされたのである。その後、海岸局の増設、日本郵船・大阪商船・東洋汽船所属の外国航路大型客船に逐次無線電信局を開設するなど船舶に無線電信局が設置されたが、技術の進歩に伴って外国との無線電信通信が実施されるようになった。
3-1 無線電報規則の制定
無線電信の技術的研究は1895年(明治28年)、マルコーニが発明した後、間もなく着手されたが、法制上取り上げたのは1900年(明治33年)、電信法が制定されたときである。無線電信はこれを勝手に施設されては困るので国家管理とし、私設規程を除いた電信法を準用した。既に述べたように、無線電信は通信の秘密を機械的に防止する方法もなく、電波は空中を独占するため公衆通信を妨げるものだとして、逓信省は当分私設を全く認めない方針をとっていた。
1906年(明治39年)10月、ベルリンの第1回国際無線電信会議で締結された国際無線電信条約及び附属業務規則が1908年(明治41年)7月1日に実施されることになっていたので、逓信省は、同年4月に無線電報規則及び無線電報取扱規程を制定し、同年6月に外国無線電報規則及び外国無線電報取扱規程を制定した。これによって無線電信の実用化、無線通信による公衆通信の取り扱いが法的に決定した。無線電話も1914年(大正3年)5月に『電信法を無線電話に準用する』ことになった。
ベルリン国際条約の施行によって無線電信の技術水準・運用者の資格・運用規準等が決められた。これに順応するために資格者の養成を逓信官吏養成所で行った。
1914年(大正3年)、ロンドンで議決された海上人命安全条約で船舶に無線装置を強制されることとなり、私設を認める必要が急迫した。また電波管制、船舶遭難通信義務等を規定する必要が生じたので、無線電信法を制定することになった。当時、武宮時敏逓信大臣の議会説明によると、差し向き新たに40隻の船舶が外国の港湾に出入するために無線電信を装置することになるのであった。
1915年(大正4年)5月、無線電信法を制定、11月から施行することになった。これに関連して同年10月私設無線電信規則及び私設無線電信通信従事者検定規則が制定された。
3-2 無線電信局の開設
無線電信の研究を始めた初期に、実験のために作られた実験室及び月島・品川第5台場などの数多くの試験用無線電信施設は別として、逓信省が正式に公衆通信に用いるために開設した無線電信局は、1908年(明治41年)5月に開局した海岸局の銚子無線局と船舶局の東洋汽船株式会社所有の北米航路豪華客船天洋丸無線電信局が最初で、ついで同年内に潮岬(和歌山県)、角島(山口県)、大瀬埼(長崎県五島諸島)、落石(北海道)の4海岸局と北米航路客船の日本郵船株式会社所有丹後丸、伊予丸、加賀丸、安芸丸、土佐丸、信濃丸、東洋汽船株式会社所有香港丸、日本丸、地洋丸の9隻に船舶無線電信局を設置した。その後も引き続いて遠洋航路客船に無線電信局を設置するため、逓信省は日本郵船・大阪商船・東洋汽船の3株式会社に官設の船舶無線電信局の設置に協力するよう要請するとともに、海岸局の増設も計画した。
無線電信局の開設にあたって必要な通信従事者の資格条件については、ベルリン条約では次のように要求している。
無線電信機器の機能について考慮を払うほかに、満足すべき通信技術の技能保持を要求し、特に船舶局の通信従事者はを必要とする。
- 一定の速さの欧文モールス符号の送受信能力
- 機器の調整能力
- 通信の秘密を守る宣誓
わが国でも、1908年(明治41年)7月1日を期して国際無線通信を開始するにあたり、通信官吏練習所(1909年(明治42年)11月に逓信官吏養成所と改称した)において条約上の第一級資格者を養成し、これを官設無線電信局に配置した。
陸上の無線電信局として遠距離通信・対外通信のための無線電信局は、はじめの銚子・落石等の海岸局を利用して試験を行ったが、無線電信の通信距離が増大されるに伴い、従来、船舶と陸地間または船舶相互間に限られていたものを海底線の代用として陸地相互間の通信にも使用されるようになった。長崎及び富貴名(台湾)の両無線電信局は、長崎と淡水(台湾)間に敷設された海底電信線が不通となった場合、それに代わって日台間公衆電報の取り扱いをするために、1912年(明治45年)6月に開設された。また、1913年(大正2年)10月に起工された船橋海軍無線電信所は1915年(大正4年)に完成したが、逓信省もこれを使って同年8月から新聞放送の試験を行い、翌年9月21日逓信省無線電信局が開設され、11月には船橋局とハワイのカフク局間の無線電信連絡が始まった。そのほか、1914年(大正3年)12月TYK式無線電話を鳥羽・合志島・神島に設備して公衆電話の送受信を開始した。
1914年(大正3年)12月に、銚子・富貴名(基隆)・大連の各無線電信局では、中央気象台から発信される暴風雨警報(英文)の放送を開始した。
1921年(大正10年)6月に、船橋無線電信局は船舶あての新聞無線電報及び気象報の放送を開始した。
3-3 初期の通信機
1846年、英国のファラデーによって電気力線と磁気力線の相関から、放射現象の振動の根源は力線であり、また、伝播の媒体はエーテルであり、光は振動によってエーテル中を伝達され、電気は針金を通って伝達されるが、振動によっても伝達されるという考えが論文として発表された。これをうけて、英国のマクスウェルが電磁方程式を導き出し、電気力線の時間的変化が磁力線の時間的変化の割合に比例するという相互関係を証明したことから電波の存在が予想された。これを実験的に証明したのはヘルツである。ヘルツは、電波を検知する方法や、自由自在に電波を出したり止めたりする方法を考案し、1888年実験装置によってマクスウェルの理論を実験的に証明した。
ヘルツの実験装置は第1図のように、1次回路でインダクションコイルと火花で高い電気振動を発生し、これが空中に放射する(電波)。2次回路は独立している。コヒーラーの発明される以前であるから、2次回路に誘電した電圧で発生する火花で電波の存在を確認したと思う。実験はもちろん実験室で行ったものであるから、2次回路の位置は種々変更して行われたが、両回路の距離を大幅に変えることはできなかったから2次回路に誘発される強さは大差がなかったという。
同調性に関してはヘルツの実験で予見されていた。当時の実験で発生した電気振動は図で見るとおり非常に短い波長のものであった。ファラデー、マクスウェル、ヘルツの3時代のたゆまない実験と探究の結果は、振動電気-振動がある速さになると空中に放射されることや、放射されたエネルギー(電波)は光とほとんど同じ速度で伝播されることが実証されたことであるが、さてこれを人類の生活に役立たせる工夫が問題であった。
1892年(明治25年)のブランリーのコヒーラー検波器の発明、翌年の水野敏之丞博士の特殊検波器の発明だと、電波を検知する方法は発見できたが、遠距離間伝達の研究がなかなか進まなかった。
マルコーニは、電線を空中高く張って(アンテナ)、これと地上との間で火花放電を行い電気振動を発生するという構想で実験を重ねて、1895年(明治28年)電波式の無線電信送受信に成功した。マルコーニ以前においても、長岡半太郎、テスラ(アメリカ)、クルックス(イギリス)、ヒューズ(イギリス)たちの学者が電波の遠距難通信の実用化について理論的・定量的に得心な研究を行っていたが、空中線と接地とによって実用化に成功したのはマルコーニの大きな功績である。
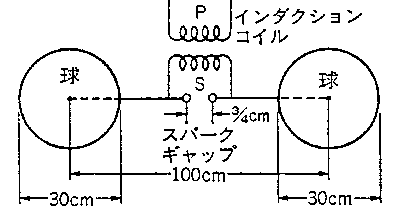
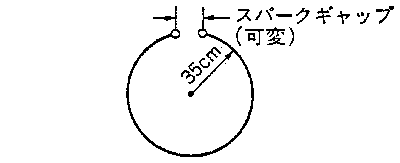
1次回路と2次回路はほぼ同調の状態にある。
電波を受けて振動電流を誘発し、その電圧に応じてギャップで火花を発生
マルコーニは空中線の高さと形状について工夫と研究を重ねながら、インダクションコイル、コヒーラー、検波器の改良などで、通信距離の増加に着々と成功した。 第2図(a)は初期の送受信装置、 同(b)は受信装置のコヒーラー、デコヒーラー、印字機である。
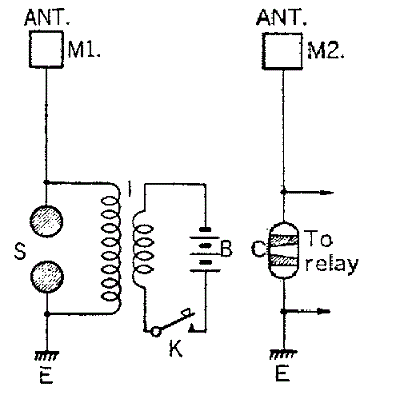
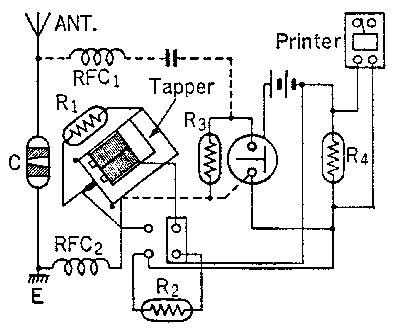
記号 K:電鍵、B:電池、E:アース、C:コヒーラー、M1,M2:金属缶、S:スパークギャップ、
I:インダクションコイル、C:コヒーラー、RFC1、RFC2:高周波チョーク、R1,R2,R3,R4:火花消去抵抗
インダクションコイルと火花で構成する送信装置とコヒーラー検波器とモールス印字機を組み合わせた受信装置は、初期の無線電信機としては便利なものであったが、インダクションコイルの構造や性能は各国がその改良に努力を払った。そのなかでも日本の安中電機製作所の製品は、安中常次郎社長の寝食を忘れてまでの研究努力が実って群を抜き、国内製品のみならず、海軍省の行ったドイツやイギリスの製品との性能比較においても最優秀の名声を獲得し、海軍36式無線機を成功に導いたことは特筆すべき記録である。逓信省の計画した対陸遠距離無線亀信及び1908年(明治41年)に開始した船舶無線電信機や海岸局無線電信機にその偉力を発揮した。一方受信機においても、コヒーラーに代わる検波器の研究が進められていたが、1903年(明治36年)に浅野応輔が水銀検波器を発明した。これはわが国での検波器の最初の発明とされ、ついで佐伯美津留の磁石鉄粉検波器、鳥潟右一のタンタラム検波器(電解検波器の一種)及び鉱石検波器の発明から天然鉱石の整流作用を利用する鉱石検波器の研究が急速に進出し、佐伯技師のエックス検波器、紅亜鉛鉱対黄銅鉱検波器など、鉱石単独のもの、2種の鉱石を組み合わせたもの、鉱石と鋼または白金の紬針の先端の接触など各種の鉱石検波器が実用化され、これと高感度の受話器とを組み合わせて、コヒーラーによる印字受信から、より便利で感度良好な調音受信へと改善されていった。
この間に、遠距離無線通信を成功させるため長波の利用や大出力の送信機の製作に研究が進められ、1901年(明治34年)フェッセンデンの高周波発電機の製作がインダクションコイルから強力電源時代の端緒をつくり、更に1903年(明治36年)パウルゼンの電弧発振機の成功によって持続電波の大電力送信機の研究の道が開かれた。その年、わが国ではインダクションコイルに代わって、高周波発電機を電源とする火花送信機で、長崎・基隆(台湾)間630海里(1,180 km)の長距離無線電信の試験に成功している。1906年(明治39年)ド・フォーレが三極真空管を発明し、また同年、フェッセンデンはかれが発明した高周波発電機を使用して無線電話の実験を試みた。1907年(明治40年)、鯨井博士は鉱石の有する検波作用(整流作用)を発見し、天然鉱石や人工鉱石の検波器の実用化へ大きな功績を立てた。1906年(明治39年)アレキサンダーソンの高周波発電機の発明は、発電機で発電する高周波(無線周波)をそのまま長波持続電波を送出する送信機として、長波大電力送信装置に使用された。一方、火花送信機においても、ドイツのウィーン教授が、空気中の火花間隙を0.3ミリメートル以下にしたときに起きる瞬滅火花効果の発見によって、回転火花間隙・同期火花間隙・分割火花間隙など、できるだけ火花のダンピング効果を利用しようとする工夫が次々と発明された。1913年(大正2年)佐伯技師が瞬滅火花間隙に着目したことはまさに火花送信機の革命とも称すべきもので、各国においてこの方式を研究し、短期間のうちに普通火花式に代わって瞬滅火花式の時代を生み、真空管を使用する持続電波の発達と並行して、鳥潟博士らの発明にかかる複式瞬滅火花による持続電波によってTYK式無線電話の成功を見た。瞬滅火花式無線電信は第二次世界大戦のころまで、実用に供された。 第3図に理論回路を示す。1次回路は火花間隙の瞬滅効果によって2、3回の火花放電で終わり、火花間隙のため回路は断線状態となる。2次回路はL1から移送された衝撃的振動で振動電流を誘発するが、L1に逆移送することがないためアンテナ回路に同調した単一振動が回路抵抗と電波発射抵抗の消耗で持続する。したがって損失の少ない単一同調電波を送出する。
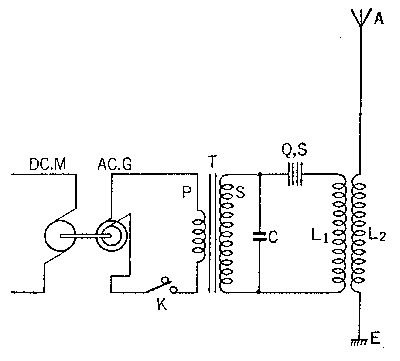
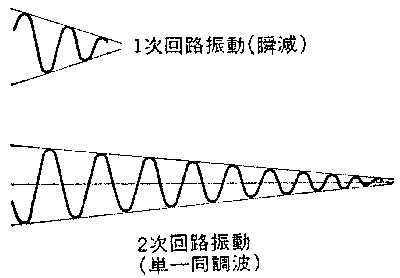
DC.M: 直流モータ、AC.G: 交流発電機、K: 電鍵、T: トランス、C: コンデンサ、
Q. S: 瞬滅火花、L1: 1次コイル、L2: 2次コイル、A: アンテナ、E: 接地
第5図はQS (Quenched Spark: 瞬滅火花放電) ギャップの構造の略図を示す。ギャップはマイカリングの厚さによって決まる。逓信省型は0.1ミリメートル、テレフンケン型は0.2ミリメートルである。ギャップの対向面は円形で銀板を張りつけ精密に加工された平面である。逓信省型はギャップが0.1ミリメートルで瞬滅効果は最高とされるが、片側を回転して放電面に生じる火花の位置を変更し放電面全体に平均した火花を発生させること、ギャップにアルコールと空気を混合した圧縮ガスを吹き込んで、冷却と気圧によって瞬減効果を増加させること、アーク防止、火花による炭化物の発生を防止することの3点に対する処置が考案された。テレフンケン式その他の瞬滅火花間隙はほとんどが0.2(マイカリングの厚さ0.2ミリメートル)を使用していた。
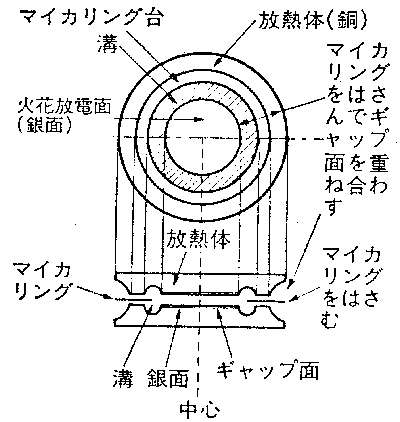
1914年(大正3年)ロンドンで締結の海上人命安全条約に基づいて外国航路の特定船に無線電信設備が強制されることになり、わが国でも無線電信法、私設無線電信規則、私設無線電信通信従事者検定規則が制定され、既設無線局の普通火花式送信機は瞬滅火花式に改装されており、新規則によって設備される無線電信機はすべて瞬滅火花送信機、鉱石検波器と三極真空管検波器を併装する同調式受信機であった。海軍の船橋無線局が1915年(大正4年)、対ハワイ通信の実験に使用したものも250kW瞬滅火花送信機と鉱石検波受信機(翌1916年(大正5年)に真空管検波受信機に改装)であった。船橋は対外公衆電報取り扱いのため逓信省は海軍省の施設を共用することとして、1916年(大正5年)11月16日、日本‐ハワイ間の無線電信を開始した。その時の無線機は次の仕様になっている。
| 局名 | 送信機 | 受信機 |
|---|---|---|
| 船橋 | 250kWテレフンケン瞬滅火花式 | 真空管ヘテロダイン式 |
| ハワイ | 300kWマルコーニ回転火花式 | 真空管ヘテロダイン式 |
海外無線通信の取り扱い増加に対処して磐城無線電信局の建設は1918年(大正7年)から計画されたが、富岡受信所が1920年(大正9年)5月、原町送信所が翌1921年(大正10年)3月に完成した。
| 原町送信所送信設備 | 富岡受信所の受信設備 |
|---|---|
|
電弧発振機 350kW 1台(後に2台)、波長14,600m 特別高周波発振機400kW 1台、波長5,000m 空中線、傘型、主塔高さ200m、地面外径17m、塔上外径1.2m、総重量11,000トン 鉄筋コンクリート製(すべて国産品) |
真空管式長波持続電波受信機、低周波増幅一段電話受信機。 空中線はループアンテナ、逆L型アンテナ 大正11年米国製受信機及び空中線を導入して通信能率の向上を図った |
海上通信は1908年(明治41年)天洋丸と銚子海岸局との間で船舶公衆無線電報取り扱いが開始され、太平洋航路に官設無線電信局が次々と開局された中で1910年(明治43年)10月、東京高等商船学校練習船大成丸に無線電信が設置された。1908年(明治41年)5月天洋丸に無線電信が設置されてから大成丸が第17番目にあたるが、当時の客船の公衆無線電報取り扱いを主目的とした逓信省の基本方針から見れば特異な存在であったといえる。
1915年(大正4年)から実現した特定船舶の無線電信装置強制によって船舶用無線電信機の製作が一種の花形産業化したが、高度の技術と経験を必要とする関係から、安中電機製作所(逓信省式無線電信機)、日本無線電信株式会社(テレフンケン式無線電信機)の2社が船舶用無線電信機の製造に全力をあげた。
船舶無線電信局を相手とする海岸局、気象局、航行警報及び船舶無線新聞放送局は早くから真空管式送信機を使用したが、その中で神戸海洋気象台の送信装置は3kWアーク送信機を使って特色のある音色で船舶通信士の耳を喜ばせてくれた。
船舶無線電信局が正式に真空管式送信機を指示されたのは昭和2年であるが、初期においては補助送信機になお瞬滅火花式を残していたことも過渡的な制度として、使い慣れた機械の信頼性に依存したいという人間の心理の妙とでもいうか、興味深い事実であろう。